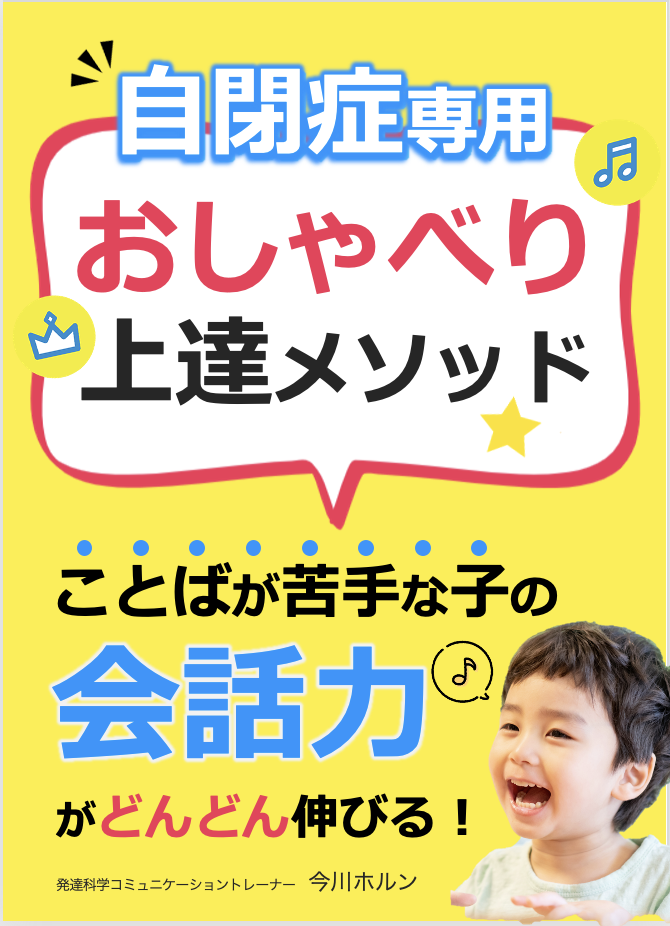目次
おうちでママがコミュニケーションをとるだけで知的障害児は量を理解できるようになる
小学校低学年で習う算数の中には数と計算、図形、量の測定がありますよね。
療育施設で行われるトレーニングのカリキュラムにも含まれていることがあるんです。
実は、おうちでママがコミュニケーションをとるだけで知的障害児の量の概念は習得することができます!
なぜなら、新しいことを覚えるのが苦手な知的障害児には、普段から見慣れているものや慣れ親しんだものに囲まれたおうちの環境こそ、反復して学ぶことができ、定着につながるからです。
そのためにはママが子どもの得意なことや特性を理解する必要があります。
好きなことよりも、できることを知ることで子どもの発達はより加速しますよ。
子どもにとって大好きなママがいて、安心できる環境で、反復して体験することができるから、知的障害児の数の理解は、より深まるのです♩

わが家の知的障害児が量を理解した!
わが家の知的障害のある太陽くんは支援学校1年生ですが発達年齢は2歳です。
ことばはまだでておらず、理解の遅れもあります。
私は太陽くんの親なのに…彼の好きな遊びもわからずコミュニケーションの取りづらさに困っていました。
そこで、なんとかコミュニケーションを取れるようになりたい!と思った私は、まず太陽くんはどういうことができるのか、何が得意なのか、観察をすることから始めました。
すると、目で見たり、手で触れたり全身を動かしたりして情報を取り込んでいることが得意だということがわかったのです!
その得意なことを活かして、量を比べることを日常生活に取り入れていくようにしました。
具体的には、好きなおやつの量を多い方と少ない方を用意し、どちらがいいか選ばせるようにしたのです。
多い方を選ぶ時は「多いね」、少ない方を選ぶ時は「少ないね」と声かけをしていくと、コミュニケーションをとることもできます。
選択した時に「多い方を選べたね!」と接していったことで、「多い方どっち?」の質問で多い方を選ぶことができるようになりました。
コニュニケーションも取れて理解力もついて太陽くんは好きなおやつを食べれるため、一石三鳥の効果があったのです^^

おうちで毎日の接し方を変えるだけで知的障害児の量の理解はぐーんと伸びる
小学校低学年の知的障害児は授業についていけなくても大丈夫。
今からでも遅くありません!
おやつの時間、ご飯の時間、遊んでいる時間など、お子さんとコミュニケーションを取る際は発達のチャンス!だと思って接してあげてください^^
ママは「量の概念を理解できるようになる」接し方に変えて、お子さんの理解力をぐーんと伸ばしちゃいましょう♩

知的障害児が遊びの中で量を理解できるようになるママのコミュニケーションテク
①子どもの目から入る情報をポジティブにするために「笑顔」で、耳から入る情報をポジティブにするために「優しくゆっくりと」声をかけるように接しましょう。
②好きな食べ物や好きな遊びを利用して、分量の異なる2つを提示します。
③どちらが大きい(多い)?と尋ねるようにしましょう。
※この時に理解ができていなくてもいいです!
③選んだ方について補足の声かけをします。
(例)「大きい方選んだね!」
「小さい方選んだね!」
④最後に、ハイタッチなどスキンシップをとりながらママは「どうぞ」しましょう。
日常生活の中でこのテクニックを使って接していくと、子どもの理解は少しずつ深まっていきます。
毎日のコミュニケーションをこのテクニックに置き換えるだけで継続して取り組むことができるため、理解力がぐーんと伸びやすくなるのです^^
子どもの発達を促したいママはぜひやってみてくださいね♩

発達科学コミュニケーション
トレーナー ひがしひかる