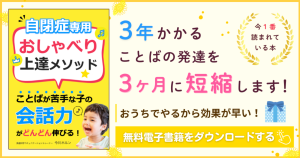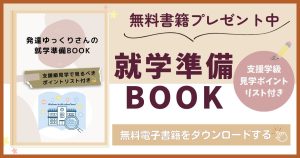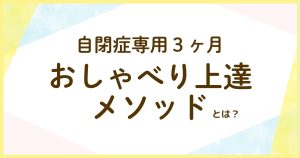目次
感情の境界線を引けば自閉症の子の癇癪に巻き込まれなくなる!
子どもに大声で泣かれたり、床にひっくり返って癇癪を起こされたとき、「どうしてこんなに泣くの?私のせい?」「私の方が泣きたいよ…」そんなふうに、心がザワザワした経験はありませんか?
実はこれ、ママの心が弱いわけでも、ネガティブ思考が強すぎるわけでもないのです。
心理学的に見ると、「子どもの感情」と「自分の感情」の境界線があいまいになっていることで、相手の感情を“自分のもの”として引き受けすぎてしまっている状態。
本来、「子どもが泣く」という行動は、子ども自身の課題=感情の脳の発達の未熟さによるものなのです。
ママがその感情を「自分のせい」として抱え込んでしまうと、感情の境界線がなくなり、癇癪に巻き込まれてしまいます。
子どもはママを責めているわけではなく、まだうまく感情を言葉にできないだけ。
感情のコントロールを担う脳のエリアがまだ未発達なのです。
だからこそ、必要なのは「この怒りや泣き声は、子どもの感情。私はそれに巻き込まれなくていい」と心理的な線引きをすること。
これは冷たい対応ではありません。
むしろママが自分の感情を守ることで、落ち着いた状態で子どものそばにいられるようになるんですよ。

今、感情の境界線を引くことが子どもの心の安定に繋がる
「感情の境界線」を引けるようになることで、子どもの癇癪に巻き込まれなくなり、自分の心もすり減らさずにすみます。
結果として、子どもも安心して落ち着ける。そ
の安心感が、やがて子どもの情緒の安定にもつながっていきます。
今この視点を持つことができれば、「泣かれる=自分が責められている」と感じていた心のクセが、少しずつ和らいでいきます。
そして境界線を持った関わりは、ママの安心感を通して、子どもにも落ち着きを届けてくれるようになります。
そんな親子の好循環が生まれてくるのです。

↓↓↓

↓画像もしくは下記URLをクリック!
https://www.agentmail.jp/lp/r/18470/156221/
私の心がふっと軽くなった「これは娘の感情なんだ」という気づき
ある日、娘が何をしても癇癪を起こし、床に寝転んで泣き叫んでいました。
私は「また始まった…」と心がざわつき、涙が出そうに...。
その時ふと、心理学で学んだことを思い出しました。
「娘が泣いているのは“娘の問題”で、“私のせい”ではない」そう考えてみたんです。
すると、不思議と心がスーッと落ち着きました。
私はただ、娘のそばに静かにいて、「大丈夫だよ」と伝えるだけにしました。
そのとき気づいたのは、子どもが泣くことと、自分が責められているように感じることは別だということ。
娘は私を責めているのではなく、ただ、自分の感情を出しているだけだったのです。
それからは、「これは娘の感情」「私は私の感情を守っていい」と、感情の境界線を引けるようになりました。
その変化が娘にも伝わったのか、癇癪が落ち着くのも少しずつ早くなっていったのです。

自閉症の子の感情に巻き込まれないための3ステップ
子どもの癇癪に巻き込まれず、冷静に向き合うためには、まずママ自身の「心の境界線」を作ることが大切です。
次の3つのステップで、少しずつ“線引き”の感覚を養っていきましょう。
ステップ①:「これは誰の感情?」と問いかける習慣を持つ
子どもが泣いたとき、自分がイライラしたとき、まずは「これは誰の感情かな?」と立ち止まってみましょう。
泣いているのは子どもの感情。
責められていると感じるのは、自分の心の反応。
分けて考えるだけで、巻き込まれにくくなります。
ステップ②:気持ちを言葉にして自分に話しかける
「私はいま、混乱してるな」「つらくなってきたな」と、自分の気持ちをそのまま言葉にしてOK!
感情に名前をつけて認めてあげるだけで、脳が安心を感じやすくなります。
ステップ③:「そばにいるだけでいい」と自分に許可を出す
子どもを泣き止ませようと必死になるより、「そばにいるだけでいい」と思えたほうが、親子の安心感は高まります。
それは“無力”ではなく、“信頼して見守る力”です。
感情の境界線を育てることで、ママの心も軽くなり、子どもの癇癪を見守る力が育っていきますよ。
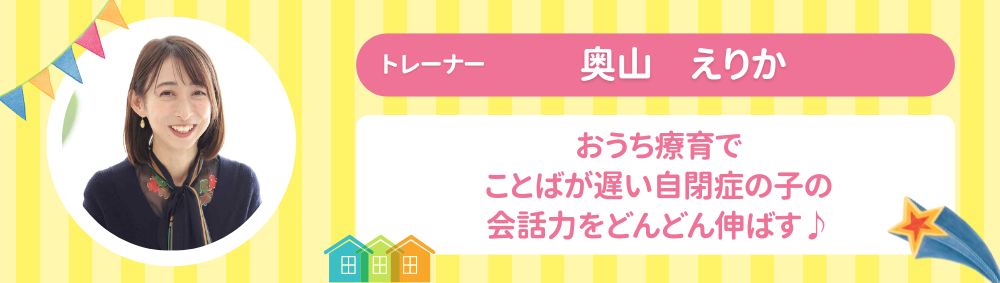
公認心理師、5歳男女双子のママです。無発語だった重度知的障害・自閉症の娘とことばと心が通い合う感動の毎日を過ごしています。
育たない脳はありません!一緒におうちでお子さんとのことばのコミュニケーションを叶えていきましょう♪