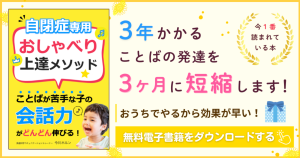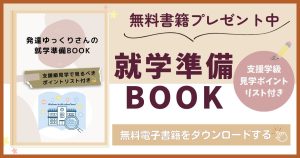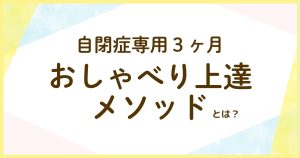お口を動かすきっかけになる親子のもぐもぐ競争
「ご飯を食べるとき、ちゃんと噛んでるのかな?」
「もしかして、丸呑みしてる⁉︎」
「飲み込みづらそうで、見ていてドキドキ…」
そんなふうに、子どもの “もぐもぐごっくん” に不安を感じたことはありませんか?
知的障害のある子どもたちは、「噛む」「飲み込む」といった一連の動作がうまくいかないことがあります。
口の周りの筋肉や舌の使い方が苦手だったり、動かし方のイメージがつかみにくかったりするのです。
そんなときにおすすめなのが、「ママともぐもぐ競争」。
ママが子どもの目の前で、少し大げさにもぐもぐ・にこにこしながら一緒に食べてみるだけで、子どもの表情がふっとやわらぎ、お口の動きが変わりはじめます。
“競争” といっても勝ち負けではありません。
「ママも食べてるよ」
「どっちが早いかな〜?」
「おっ、上手にもぐもぐしてるね!」
そんなふうに、楽しみながら自然にリズムや動かし方を伝えていく。
まるで遊びのような関わり方です。
子どもにとって、信頼しているママが一緒にやって見せてくれる安心感と「同じことをしている」楽しさが、お口を動かすきっかけになるのです。

ご飯の練習が伸ばすお口の力
幼稚園や学校では、先生がずっとそばで子ども一人ひとりの食べ方を見守ってくれるとは限りません。
ふとした瞬間、目を離したすきにうまく噛めずに喉に詰まらせてしまう――
そんな「まさか」のリスクを減らすためにも、家庭での練習がとても大切です。
また、今のうちからお口の動かし方を “楽しく” 身につけておくことで、「食べる力」はもちろん、「話す力」や「脳の発達」にまでよい影響が広がります。
もぐもぐすることで口の筋肉が育ち、表情も豊かに。
言葉が出やすくなったり、人とのやりとりがスムーズになったり。
実は、ご飯の時間そのものが子どもの力をぐんと育ててくれる大切な時間なのです。

一緒に食べることで育ってきた知的障害のある息子の “もぐもぐ力”
私には身体障害と重度知的障害のある息子がいます。
手先が不器用で、スプーンを持つのもひと苦労。
生まれたときから医療ケアが必要で、ケアを卒業した今も、食べる練習は続いています。
そんな息子のご飯を見守りながら、私はいつも後回しで自分の食事をかきこむ日々を送っていました。
だけど、あるときふと考えたんです。
「どうして私だけ、こんなに急いで食べてるんだろう?」
「どうして私は、味わう時間を持てないんだろう?」
それならいっそ、一緒に食べてみよう。
そう思ってはじめたのが “もぐもぐ競争” でした。
息子の目の前に同じご飯を並べて、「どっちがたくさんもぐもぐできるかな?」ともぐもぐ競争開始。
私がもぐもぐしてみせると、息子も一緒に口を動かし始めたのです。
そうしていくうちに少しずつもぐもぐが上手になっていき、噛んで咀嚼する力が育っていきました。
それだけではなく、私が食べている「これちょっと難しいかな…」と思うものにも興味を示し、自分から手を伸ばし、「食べてみたい」という気持ちが芽生えてきたのです。
親子で競うご飯のもぐもぐ競争
やり方はとてもシンプルです。
① お母さんもご飯を用意して一緒に食卓に座る
子どものご飯だけでなく、自分の分も準備して「いただきます」。
正面に座って目線を合わせましょう。
②「一緒に食べよう」「どっちが上手に食べられるかな?」と声かけ
「ママも一緒に食べるね」「〇〇くん(ちゃん)とどっちがたくさんもぐもぐできるかな〜」など、少しワクワクするような声かけがコツ。

③ 食べるタイミングを合わせて、「同じものだね」と実況中継
子どもと同じタイミングで同じものを食べ、「〇〇くん(ちゃん)と同じご飯だね」「一緒に食べるとおいしいね」と言葉で伝えていきましょう。
④ 子どもがママの食べ方に興味を示したら…かじりとりのチャンス!
ママの口元を見ていたり、「それなあに?」と関心を持ったときがチャンス。
「一口食べてみる?」「ママと半分こしてみようか?」と誘って、“かじりとり” にも挑戦してみましょう。
この “もぐもぐ競争” を繰り返すことで、
- 「ママと同じものを食べている楽しさ」
- 「ママの動きを見て真似すること」
- 「ちょっと難しい食べ物への挑戦」
が自然に育まれていきます。
そうやって育った「お口の力」は、しっかり噛む・ごっくんするという基本の力だけでなく、将来の “おしゃべり” にもつながっていきますよ。
発達科学コミュニケーション
トレーナー 岩村 萌永(いわむら もな)