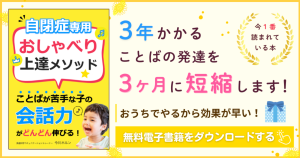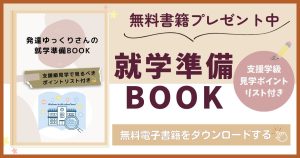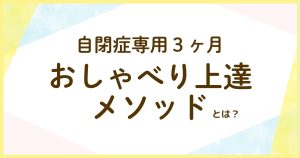目次
並べる「好き」をきっかけにすればお絵描きもできるようになる!
「うちの子、お絵描きどころかおもちゃで遊ぶのも苦手で…」
そんな悩みを抱えるママに伝えたいのは、「遊ばない」のではなく、「今は新しいことを受け入れにくいだけ」だということです。
自閉症の子どもたちは、脳の特性から“安心できること”に強く集中します。
逆に、未知の刺激には不安や混乱を覚えやすいため、遊びのレパートリーが極端に少なくなるのです。
「クレヨンで絵を描いてみようよ」と言っても、並べることで安心している子にとっては、それが“今できる精一杯”の遊び方。
だからこそ、「描いてくれない」「全然遊びが広がらない」と焦る必要はありません。
無理に興味を広げるのではなく、“今の好き”を起点にしてあげること。好きなら何度でもクレヨンを並べさせてあげて下さい。
それが、子どもの脳の発達を加速させる第一歩になるのです。

「好き」を広げるタイミングは今だからこそ効果的
脳の発達には、タイミングがあります。
特に未就学期は、脳が柔らかく吸収力が高い時期。
今、子どもが夢中になっていることに寄り添い、それを少しだけ広げていくことで、大きな変化が起きやすくなるのです。
「並べる遊びしかできない…」と感じる時こそ、実は伸びしろが眠っているタイミング。
そこにママの関わり方が加わると、「描く」「塗る」「消す」といった新しい動きがどんどん加わっていきます。
さらに、お絵描きができるようになると、園や学校での活動にも自信を持って取り組めるようになり、他の子との関わりも増えていきます。
今の「好き」を起点にすることで、子どもの世界がどんどん広がっていくのです。

並べていたクレヨンが、“描ける喜び”に変わった日
娘はあらゆるものを「並べる」のが大好きでした。
ブロック、宝石のおもちゃ、マグネット…何でも並べて、眺めて、壊して繰り返して満足する。
お絵描きしようと誘っても、色鉛筆やクレヨンを箱から出してずーっと画用紙の上に並べて遊んでいて、隣で絵を描いて見せても全然ダメ。
うちの子はお絵描きは無理なのかな・・・と思っていました。
そんなある日、「キットパス」という窓ガラスに描いても簡単に拭いて消すことができるクレヨンがあることを知って購入しました。
娘は窓の外の景色をみるのも、窓に反射しているものを見るのも好きだからです。
早速、娘が窓を見て何やら遊んでいる時に、私が窓にくるっとクレヨンで丸を描いて見せました。
すると娘は「えっ」という感じでじっと見てから、いつもは並べてばかりいるクレヨンを手に取り、初めてクレヨンで描くという行為をしたのです。
「描けたね〜!」「すごいすごい!」と声をかけると、娘はニコッと笑って、何度も描いては見せてくれました。
描いたあとには、ティッシュで一緒に拭き取って「消えたね〜」と伝えると、それもまた楽しい遊びになります。
こうして「描く感覚」を覚えた娘は、すぐに画用紙にも描くようになり、色鉛筆やペンも使ってお絵描きが大好きな子になりました。
幼稚園でも、先生にチョークを出してもらい、黒板にお絵描きしては消すのが娘の楽しみになりました。
ずーっと「お絵描きしない子」だったあの頃からは、想像もつかないほどの成長です。

“描ける”まで育てる!遊びのステップ3
ステップ1:クレヨンで描かなくてOK!好きに遊ばせてあげる
「わあ、きれいに並べたね」
「赤・青・黄色だね」
こんな風に、やっていることや見ているものをそのまま実況中継のように声かけをしながら、並べる行動をしっかり受け止めます。
ステップ2:描いて見せる → 真似して描く!
ママが描くのを見せると、クレヨンを手に取り、同じように描き始める時が必ずやってきます!
興味があるものをかけ合わせて、窓や鏡、お風呂で描けるクレヨンでお絵描きもおすすめ。
「描けたね〜」「楽しいね〜」と声をかけながら、嬉しい気持ちを共有します。
ステップ3:描いたら消すまでが遊び→紙やおもちゃにも広がる
拭き取る楽しさもセットにしちゃいましょう!
慣れてきたら、「おえかきせんせい」などの遊び道具も取り入れて、「描ける場所」が増えることで遊びが定着していきます。
好きに寄り添って遊びを広げていきましょう!
発達科学コミュニケーション
トレーナー 奥山えりか