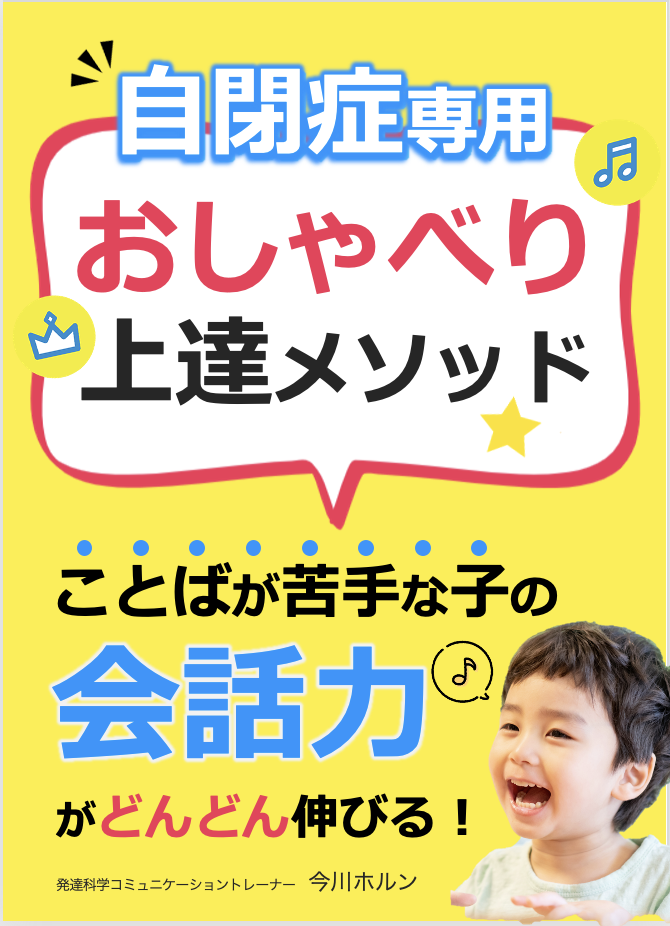目次
学校を不安だらけの場所から居心地の良い空間へと変えたい!

皆さんは子どもの頃、小学校が好きだったでしょうか?
それとも、ちょっと苦手だったでしょうか?
いやいや、むしろ嫌いだった!という方もおられるかもしれません。
不安感やこだわりなど、様々な特性を持つ自閉っ子にとって、学校という場所は必ずしも、居心地の良い楽しい場所であるとは限りません。
もちろん、自閉っ子達の中には、学校が大好き!というお子さんもおられると思いますが、自閉っ子ママの大半は、どうやったら学校を好きになれるのか、、!?と頭を悩まされておられるのではないでしょうか。
嫌な場所へ無理やり行かせても良いことは一つもありません。
ましてや脳の発達が未熟な自閉っ子達にとってネガティブな環境というのは全くもって好ましくありません。

なぜなら、脳の発達に大切なのは、ポジティブな環境で落ち着いて過ごし、その中で成功体験を積んでいく事だからです。
1日の大半を過ごす学校が子どもたちにとって安心安全な場所で、楽しい!と思える場所でなければ、脳の発達には何もプラスの影響はありません。
そのため、学校という場所を自閉っ子たちが楽しく安心して過ごせる場所にするための工夫や環境整備が必要不可欠なのです。
今回は、学校の先生やお友達などを我が子の強い味方にする!!
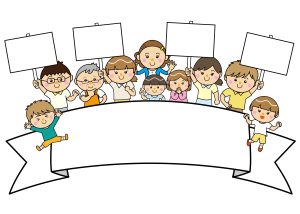
我が子の応援団のような存在になってもらえるような、そんな関係作りのヒントをご紹介します☆
自閉っ子にとって応援団が必要なワケ
私には、地域の支援学級に通う小学3年生の息子がいます。
息子には重度の知的障がいと自閉症があり、まだ発語が少なく、言葉だけを使ったコミュニケーションを図ることは難しいのが現状です。
そんな彼が地域の小学校の支援学級に行くなんて当時は無謀にも思えました。
なぜなら、私の住む地域では普通級と支援級を分けることはなく、一緒に同じ教室で過ごす、いわゆるインクルーシブ教育が行われている自治体だからです。
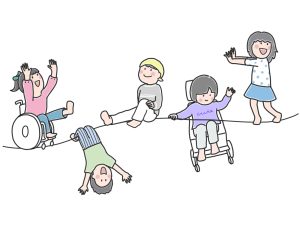
そんな場所へおしゃべりもできない息子が行って大丈夫なのか!!??
どうやって周りとコミュニケーションをとるんだろう!?
いじめられないかな??
ほったらかしにされないかな???
考えるとキリがないほどの悩みや不安に押し潰されそうになった日々を今でも覚えています。
不安は尽きないけれども、息子が少しでも学校を楽しく居心地の良い場所だと思ってもらえるようにするには何ができるだろうか?
できる事はきっとあるはずだ!と考えて行動に移した結果、小学3年生になった今、息子は学校が大好きになり、毎日ニコニコで過ごすことができています。

たまに崩れてしまった時でも、周りの先生やお友達のおかげで、上手に切り替えて色んな授業にも取り組めるようになりました!!
小3重度知的障がい・自閉っ子が大きな行事をやり切ることができたのは応援団のおかげ!

小学校の2学期は、運動会や参観、遠足、学習発表会など、何かと行事が多くて、自閉っ子にとってはストレスフルでタフな時期になることが多いかと思います。
そんな環境の中で、学校の先生やクラスメートが我が子の強い味方でいてくれたら、こんなに心強いことはないのではないでしょうか。
新しい年度が始まった1学期は、とにかく新しい教室、新しい先生、新しい友達に、まずは慣れる!ということに必死だったという自閉っ子親子も多いのではないでしょうか。
新しいクラスにも慣れて、大きな行事が控えてくる2学期。
この2学期の始まりの時期に、我が子に関わってくれている先生やお友達とのやり取りの中で、ちょっとした工夫をする事で我が子が安心して通えるかもしれない!!!
ぜひ、2学期は先生やお友達と絆や関係を深める学期にしてみて欲しいと思います!

自閉っ子が自分は周りから受け入れられている、応援されているというポジティブな感情を持てる環境であれば、苦手なことやちょっとしんどいなと思える行事でも、きっとチャレンジできるはずです!
ぜひ、この機会にお子さんに関わる先生や友達を強い味方につけて、我が子の応援団を作ってみませんか?
ママがわが子の広報になろう!学校で応援団を作るための3ステップ
ステップ1:周りからの息子に対する質問には1対1で丁寧に答える

自閉っ子の特徴というのは、具体的にわかりやすいものもあれば、一見するとよくわからないものまで、実にたくさんあるかと思います。
うちの子の場合は、まず、なぜ喋ることができないのか?そこが周りのお友達からすると最大の謎でした。
息子は集団登校で学校へ通学していますが、私も毎日学校まで付き添っています。
入学した当初、学校に着くと、朝から何度も何度も色んなお友達から「なんで、喋られへんのー??」と聞かれました。
他にも、子ども目線の質問なので、そういうところが疑問に思うんだ!というような事までたくさん聞かれました。
私はそれらの質問一つ一つ、1人1人に対して答えていきました。
一見、同じ質問をしているようでも、聞いてくるお友達によっては微妙にニュアンスが違ってくることもあったからです。
それは息子の同級生に限らず、学校の先生方も同じでした。
先生によって、支援教育への考え方、知識量、熱量などがバラバラで、それぞれの先生の目線でしっかりとお話をしないと誤解を生んだり、こちらの意図が伝わらない事があったからです。
そこで、一見すると同じ内容の質問に対しても必ず1対1で答えるようにしていきました。
ステップ2:ママが、学校の先生やお友達と、とにかくたくさん会話をする

私は、息子の同級生や先生達に我が子のことをたくさん知ってもらおう!と時間の許す限り、たくさんたくさんおしゃべりをしてきました。
いわば、私が息子の広報=プレスとして、息子を宣伝するべく、たくさんおしゃべりをする事にしたんです☆
広報というとなんだか堅苦しいイメージが湧くかもしれませんが、あえて真面目で堅苦しい会話は避けました。
会話の内容は、息子の特性や息子の好きなこと、苦手なこと、息子とコミュニケーションをどうとるかや、息子がジェスチャーで何を伝えたいか、こうしたらこう感じるんだよーなど、息子に関する些細なことについてもたくさん話しました。
また息子に関することだけでなく、たわいもない内容や雑談も交え、とにかく楽しく会話する事を心掛けました。
ステップ3些細な場面でも必ず感謝の言葉を相手に伝える

おしゃべりをする中で私が必ず心掛けていたことがあります。
それは、感謝の言葉です。
お友達には、「いつも〇〇(息子)を気にしてくれてありがとう」、
先生方には、「いつも配慮や授業を工夫して下さってありがとうございます」
と伝えてきました。
感謝の言葉は最強の魔法の言葉だと思います。
感謝をすることによって、周りの人たちがほぼ100%息子の味方になってくれるからです♪
毎日学校に滞在しているものの数十分の会話ではありますが、息子の事を細かいところまで、リアルに知ってもらうようにたくさんの会話と感謝の言葉を伝えてきました。
この日々の会話のおかげで、息子のことを自分ごとのように考えてくれるお友達や先生が増えていき、今では親の私よりも親目線なコメントをくれたり、私が気がついていない息子の小さな成長や変化だったり、息子の困りごとについても教えてくれています。
そして小学3年生になった今、紛れもなく息子の最強の味方が学校に存在しています。
そういった周りのたくさの応援の中で、息子は日々たくさんの成長をみせてくれています。
皆さんもぜひ、学校のお友達や先生方と楽しく会話をして、お子さんのための最強の応援団作り、やってみませんか?☆
発達科学コミュニケーションリサーチャー
横田 聖子